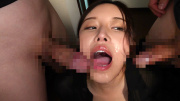最新作【大量ザーメン浴】肛門マナー教室 仕事帰りにタコ部屋で無麻酔によるアナル拡張挿入必修です 被験番号:002 若林ゆりな

【大量ザーメン浴】肛門マナー教室 仕事帰りにタコ部屋で無麻酔によるアナル拡張挿入必修です 被験番号:002 若林ゆりな
生物的に変態である。彼女は、心の底から人間として普通に生きたいと願っている。穏やかな日常、優しい恋人、ありふれた幸せ。それだけを追い求めてきた。しかし、身体の奥底に巣食うもう一人の自分が、常に彼女を支配する。理性が「いやだ」と叫んでも、肉体は正直だ。気づけば膝をつき、首輪を求め、痛みを甘く感じ、屈辱に酔いしれている。調教される自分を、どこかで強く望んでいる。これは業の深さなのか。それとも、人間という生き物の本質的な姿なのか。抑えきれない欲望は罪か、それとも自然か。誰も答えを知らない。彼女自身でさえ、ただ苦しみと悦びの狭間で揺れるだけである。